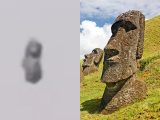モアイ像の常識が覆る!イースター島は「孤立した謎の島」ではなかった… 最新研究が明かす“文化の逆流”とは

南太平洋に浮かぶ絶海の孤島、イースター島(ラパ・ヌイ)。そこに佇む巨大な石像「モアイ」は、誰が、何のために、どうやって作ったのか、考古学における最大の謎の一つとされてきた。
その起源については、ポリネシア人が作ったという説から、一部の熱狂的な人々が唱える「宇宙人建造説」まで、様々な憶測が飛び交ってきた。しかし、最新の研究が、この長年の「奇妙な議論」に終止符を打ち、これまでの常識を覆すかもしれない。
モアイ像とは何か?
地元では「モアイ」として知られるこの石像は、東ポリネシアに位置するイースター島(ラパ・ヌイ)の人々によって作られたと考えられている。18世紀にヨーロッパの航海者によって発見されて以来、その存在は人々を困惑させてきた。
平均的なモアイ像は、高さ約4メートル、重さ12~14トンにも及ぶ。硬化した火山灰から彫り出された巨大な人頭像で、その数は島全体で1000体以上にもなるという。記録上最大のモアイ「パロ」は、高さ約10メートル、重さ82トン。さらに「エル・ヒガンテ」と呼ばれる未完成の像に至っては、完成すれば高さ21メートル、重さ150トンにも達したと考えられている。まさに驚異的な建造物だ。
最新研究が明かす「文化の逆流」
学術誌『Antiquity』に掲載された新しい研究は、このモアイ像の謎を解く鍵が、ポリネシア全域の文化的な交流にあることを示唆している。
これまで、イースター島は何世紀にもわたって外界から孤立した島だと考えられてきた。しかし、ポール・ウォリン教授らの研究チームは、太平洋の島々に点在する儀式的な遺跡の年代を「放射性炭素年代測定法」という科学的な手法で分析。その結果、驚くべき文化の流れが明らかになったのだ。
まず、西暦1000年から1300年にかけて、儀式の場を示すために一本の石を立てるという文化が、西ポリネシアから東へと広まっていった。そして最後に人が住み着いたイースター島に、その文化が最後に到達した。ここまでは従来の説と一致する。
しかし、その後に起きた「第2の波」が、定説を覆した。
西暦1300年から1600年にかけて、「アフ」と呼ばれる石の祭壇を伴う、より形式的な儀式建築がポリネシア全域で広がり始める。驚くべきことに、この「アフ」の発祥地は、なんとイースター島だったのだ。つまり、文化は東から西へ、つまりイースター島から他のポリネシアの島々へと「逆流」していたのである。

孤立していなかったラパ・ヌイの人々
ウォリン教授によると、イースター島では1300年から1400年にかけて「アフ」の神殿跡が次々と現れ、その後1400年以降になってから、クック諸島など他の中央・東ポリネシアの島々でも見られるようになるという。
さらに、この文化の逆流を裏付けるのが「第3の波」だ。イースター島で1350年頃から作られ始めた巨大なモアイ像のような記念碑が、その後16世紀にはハワイなど、ポリネシアの他の地域でも作られるようになった。
この事実は、イースター島が文化的な発信地として、他の島々と交流を持っていたことを示唆している。ウォリン教授は、ラパ・ヌイの人々が南米大陸と接触していたことを示す遺伝子的な証拠にも触れ、「彼らがそれほどの優れた航海技術を持っていたのなら、逆方向(他のポリネシアの島々)へも行けたはずだ」と語る。
イースター島を「孤立した謎の島」と見なす考え方こそが「奇妙」だったのかもしれない。モアイ像は、孤立した文明の産物ではなく、広大な太平洋を舞台にしたダイナミックな文化交流の象徴だったのである。
参考:LADbible、ほか
※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。
関連記事
人気連載
“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】
現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...
2024.10.02 20:00心霊モアイ像の常識が覆る!イースター島は「孤立した謎の島」ではなかった… 最新研究が明かす“文化の逆流”とはのページです。イースター島、モアイ像、ラパ・ヌイなどの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで