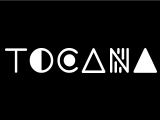あの子はひとりぼっちだった……少年の“死に方”を決めた“異常な遊び”と謎の幽霊
作家・川奈まり子がこれまで取材した“実話怪談”の中から霊界と現世の間で渦巻く情念にまつわるエピソードを再掲する。

あの子はひとりぼっちだった
2001年11月、群馬県某所で暴走族同士の乱闘騒ぎがあり、このとき1人の少年がナイフで刺されて死亡した。
被害者と加害者は、それぞれ異なる暴走族に属し、チーム同士が対立していたことから、警察はこの事件は暴走族の縄張り争いが発端であると発表し、新聞やテレビでもそのように報道された。
翌年行われた裁判では、被告少年の弁護士は、被害者が被告を卑怯者呼ばわりするなどして挑発したことが犯行の原因であると主張。衝動的に刺した結果死んでしまったのだ、と、不運な事故であるかのごとく抗弁した。
当時の新聞や雑誌を探し出して事件の詳細を改めて読んでみると、事故扱いにするには犯行の残虐性が気になった。まずナイフでひと突きして、被害者が倒れると馬乗りになり、集中的に左胸を繰り返し何回もナイフで突き刺した挙句、2リットルも出血させて死に至らしめたのだという。
しかし同時に、たしかに弁護側の言うように、計画性を見出すのが難しい事件だとも思った。
この殺人は、総勢約50名の少年たちの大乱闘の真っ最中に起きた。約50人全員が殺害現場に居合わせ、また、その多くがナイフなどの凶器を所持していたのである。
この状況では、被告少年がとくに被害者だけを殺害する目的で凶器を準備していたとは考えにくい。仲間にならって自分も武器を用意したに過ぎないだろう。被害者の口汚い挑発を聞いていた者も敵味方限らず大勢いた。誰が殺人者になっても不思議ではなく、むしろ1人しか死ななかったことが奇跡のようですらある。
倒れた被害者を執拗に刺しつづけたことも、頭に血がのぼった結果だと思えば、「暴走族に入っている不良少年なのだから、やりかねない」と、つい、納得してしまいそうだ。
しかし、それは偏見というものだ。今回、私は自分の心に巣食う、こうした常識人ぶった偏見を検めることにした。この事件の被害者が登場する体験談が寄せられ、体験者さんを取材した結果、反省したのである。
この体験談を寄せてくれた畑山里香さんも、2001年に事件が初めて報道されたときは、殺害現場が生活圏内だったことは怖いと思ったが、それ以外には特にこれといって感想を持たなかったそうだ。
里香さんは事件当時、自宅通学する20歳の大学生であり、暴走族などとは無縁の、至って穏やかな生活を送っていた。彼女が家族と共に暮らす地域は治安が良い文教地区で、一戸建ての家が立ち並ぶ住宅街が広がっている。事件が起きた場所は、この辺りの住民がよく利用する商業施設の一角だった。住宅街からは5キロほど離れているが、車で10分程度の距離だ。
群馬県内の自家用車保有台数は全国一位(2017年度)。里香さんも自動車免許を持ち、車でこの商業施設を訪れたことはあった。しかし閉店後の駐車場が暴走族のたまり場になっているという噂があり、夜間はなるべく近づかないようにしていた。だから、事件が起きると、用心してきて正解だったと改めて思った。
近所で起きたとはいえ、暴走族の世界や殺人事件との心理的な距離が縮まることはなかったのだ。そのまま何事もなければ、彼女はこんな事件のことなど、とうに忘れていただろう。

ところが、事件後しばらくして、里香さんのもとに、近所の幼馴染、石川義也さんからこんな電話が掛かってきたのだった。
「こないだ近所で暴走族同士の殺人事件があったよね。殺された方の名前がテレビや新聞に出たけど、憶えてる?」
里香さんは、うろ覚えだったが、被害者の名前を口にした。仮にここではその名を「佐藤健一」としておく。
石川さん――いや、ここからは里香さんの呼び方にならうことにしよう――義也くんは、里香さんの答えを聞くと、「その佐藤健一が、小4のとき僕たちのクラスに転校してきた高橋健一くんだったんだよ!」と言った。
――ぬいぐるみの胸に刃を振りおろしていた、あの高橋くん。
瞬時に厭な記憶がよみがえり、里香さんは気分が悪くなった。
「それ、間違いないの?」
「うん。しかも犯人は高橋くんの腹違いの弟だということだよ。少年だから氏名は公表されていないけど、そうなんだって」
聞けば、彼の友人に高橋くんが所属していた暴走族の関係者がいて、その人から直接聞いた情報だから間違いないということだった。
「僕らと同世代の男の間では、高橋くんと義理の弟の家庭事情は、ずいぶん前から知られていたんだ。僕もそんなものだけど、この辺の男には、兄弟や先輩や同級生が暴走族にいるヤツが多いし、高橋くんの家にまつわる話は痴情がらみだったから、よくネタにされていた。それに僕は高橋くんの腹違いの弟とそのお母さんに偶然会ったことがあって、そのときも、高橋くんについていろいろ聞かされた」
里香さんは少々ショックを受けた。義也くんとは小中ずっと学校が同じで、長じてからも異性であることを意識しない兄妹のような友情をつむいできたつもりだったのだ。
「なんで話してくれなかったの? 私、ちっとも知らなかった」
「なんでって。畑山さんにはわかるだろ? 僕だって知りたくなかったよ! だって、あのときのこと思い出しちゃうじゃないか!」
「あのとき?」
――高橋くんが「おまえらも、やれよ」と言ったとき。
「うん。あのときだよ。事件をニュースで知ってから苦しかった。誰かに話したかったけど、あそこに居合わせたのは畑山さんだけだから、僕が感じてる怖さを理解できるのは畑山さんしかいないって思った。
彼のあの死に方……。高橋くんは自分のぬいぐるみと同じことになって死んだわけだよね? 畑山さんは、偶然だと思う? あれは僕たちが小4の夏休み前だったね」

その頃、里香さんと義也くんは小学校4年生で、共に学級委員だった。2人は1学期の初め頃にクラス担任の先生に呼ばれて、4月に転入してきた高橋くんのことを気にかけてやるように言われていた。
しかし高橋くんは暗い目をした気難しい少年で、話しかけても無視したり、ぶっきらぼうな一言のみ返して黙りこくったり。遊びに誘っても断られるので、里香さんたちは間もなく匙を投げた。
もしも高橋くんが魅力的な雰囲気を纏った少年だったら、学級委員が頑張るまでもなく、積極的に接近を試みる子がいたかもしれない。だが、残念ながら彼は表情の変化が乏しくて、いつもなんとなく怒っているような気配を漂わせていた。また、不健康に痩せていて、服や体操着がいつも薄汚れていた。
高橋くんは、友だちができないまま、次第に学校を休みがちになり、5月の連休明けからは不登校に近い状態になってしまった。
里香さんと義也くんの学校では、欠席者に「学校だより」などの配布物を持っていくのは、学級委員の役目だとされていた。
そこで、里香さんと義也くんは連れ立って、担任教師から教えてもらった住所と地図をたよりに、高橋くんの家を度々訪ねていくことになった。
学校でみんなに配られたのと同じプリントを高橋くんに手渡すだけだから、最初のうちは簡単だった。本来、1人で事足りる用事だ。それぞれの習い事の都合により、里香さんだけ、または義也くんだけで高橋くんの家を訪ねていったこともあった。いつも、インターフォンを鳴らすと高橋くんは玄関の外に出てきて、素直にプリントを受け取ってくれた。
しかし夏休みの宿題や自由研究については、ただ高橋くんに手渡すだけではなく、宿題の範囲ややり方を説明しないわけにはいかなかった。おまけに、学校に置きっぱなしになっていた高橋くんのピアニカや習字道具も持っていくことになったので、2人で協力し合う必要が生じた。
「夏休み前に担任の先生から頼まれたときは、先生がやればいいのにと思いました。でも先生は、高橋くんのお父さんに面談を申し込んだり、家庭訪問しようとしたりしたけれど、断られてしまったんですって。それに、先生じゃなくて、クラスメートの私たちが行った方が高橋くんは喜ぶだろうって……」
仕方なく、里香さんと義也くんは、7月下旬のその日、高橋くんの持ち物や夏休みの宿題ワークブックの束を抱えて、彼の家を訪問した。
そして、荷物の量や大汗をかいてフーフー言っている2人のようすを見たせいだろうか、この日初めて、高橋くんが「上がれよ」と言った。
高橋くんの家は、当時は珍しくなかった公営の一戸建て住宅で、間取りは2DKの平屋だった。ごく小さな家だが、入居して半年に満たないこともあり、外観には荒んだ印象はなかった。
けれども、中に招じ入れられると、里香さんと義也くんはすぐにこの家の異常さに気がついた。
家具が、無い。
テーブルも椅子も、ベッドも本棚も、カーテンすら、無い。
冷蔵庫、扇風機、テレビといった家電も、一切無い。
布団も座布団も見当たらず、高橋くんのランドセルと教科書やノートが壁際の床にじかに並べられていた。
殺風景というレベルではない。生活感が皆無で、室内にうっすらと高橋くんの体臭が漂っていなかったら、空き家かと思ってしまうところだ。
高橋くんは、唖然としている2人を置いて、ずんずん部屋の奥に歩いていった。背中を向けて床に胡坐をかくと、目の前の床に置いた何かを小刻みに叩くようなしぐさをしはじめる。
「何してるの?」
里香さんが問いかけると、高橋くんは動作を止めて、「遊び」と答えたが、すぐに再び何かの作業に集中しだした。
「おい!」と義也くんが言った。彼は優しい性格で、めったに声を荒げることなどないのだが、珍しく苛立っているようだった。炎天下を歩いてきたというのに、高橋くんの家が蒸し風呂のように暑かったせいかもしれない。
「こっちを向けよ! 宿題の説明をしてやれって先生に言われてるんだよ! さっきからいったい、何してんだよ!?」
するとようやく、高橋くんは動いた。
尻を軸にしてクルッと回り、里香さんと義也さんの方を胡坐をかいたまま体ごと振り向いて、
「だからぁ、遊びだよ! ずっとこれで遊んでたんだ。おまえらもやれよ。ストレス発散できるよ!」
ぬいぐるみと大型のカッターナイフを持った両手を高く掲げてみせた。
「あのときの高橋くんの顔は今でも忘れられません。笑顔……だったと思います。でも目がイッちゃってて、ゾッとしました。それに、ぬいぐるみが、もう本当にズタズタで。さっきまでの高橋くんの動きを思い返すと、何分か、それとも何時間かわからないけど、とにかく長い時間をかけて、しつこくグサグサ突き刺していたことが明らかでした。
たぶん私は悲鳴をあげたんじゃないかと思います。怖かったから」
身震いしている里香さんに、私は「何のぬいぐるみでしたか?」と訊ねた。
「たぶんクマだと思います。布製で綿のつまった、頭から足の先までで30センチくらいの。男の子があんなもので遊ぶのは2、3歳とか、せいぜい4、5歳までだと思うんですけど、そのぬいぐるみは色が褪せていて古そうでした」
「じゃあ、高橋くんが小さな頃に買ってもらった物かもしれませんね?」
「そう思います。その後すぐに、義也くんが黙って窓を顎でさし示したので見たら、外にぬいぐるみや塩ビで出来た怪獣やお人形がいっぱい転がっていて……どれも同じように古そうで、全部ズタズタに切り裂かれていました」
カーテンの無い掃き出し窓のガラスの向こうに、物干し台を置いたらいっぱいになってしまいそうなささやかな庭があった。その地面をおびただしいぬいぐるみや人形が覆いつくしていた。真夏の日差しに傷を焙られながら。
「……宿題の説明どころではなくて、私たち、すぐに逃げ出してしまいました」

以来、里香さんは彼を見ることはなかった。二学期に入ってしばらくして、担任の先生から高橋くんが転校したことを知らされた。同じ市内の違う町に引っ越して、学区が変わったということだった。
「高橋くんが中学校にほとんど通わないで不良グループに入ったことは、男子の間ではよく知られていた。その頃には父親に引き取られて、彼は佐藤って苗字になっていたはずだ」
義也くんは里香さんに、高橋くんの母親に会ったことはあるかと訊ねた。
「あるよ。私がひとりでプリントを届けにいったとき、高橋くんと一緒に玄関から出てきて、上がっていってって言われたんだけど……」
初夏と呼ぶには早い、梅雨の晴れ間の午後。今日は塾があると義也くんが言うので、里香さんはひとりで高橋くんの家を訪ねた。
すると、高橋くんの後ろから、清楚なワンピースを着た小柄な女性が出てきた。玄関の庇の下に立ち、里香さんを見ると顔をほころばせた。ちょっと不格好だけれど美味しそうなクッキーを盛りつけた皿を持っている。
「健ちゃんのお友だち? よかったら家に上がっていって。ほら、ちょうどクッキーを焼いたところなのよ。食べていってくださいな」
痩せ形の綺麗な人で、高橋くんと面差しがよく似ていた。瓜二つと言ってよかった。優しそうなおばさんだと里香さんは思ったが、高橋くんが黙って睨みつけてくるので、「用があるので帰ります」と言った。
すると、おばさんは「じゃあ、ここでお一つどうぞ」と里香さんにクッキーを勧めた。華奢な両手でクッキーの皿を捧げ持ち、どうぞどうぞと前に突き出してくる。甘い匂いに鼻孔をくすぐられ、「じゃあ1つだけ……」と里香さんは手を伸ばしかけたのだが、
「そんなもの食わない方がいいよ!」
高橋くんにいきなりクッキーの皿を叩き落とされた。驚いて固まった里香さんの足もとに、クッキーと皿が粉々になりながら飛び散った。
里香さんがこの話をすると、義也くんは怪訝な顔をした。
「畑山さん、高橋くんの義理のお母さんは、大柄で太り気味の、いつも派手な服装をした女性だよ? さっき言ったけど、僕は偶然、会ったことがあるんだ。豪快な感じのおばさんで、華奢で清楚なワンピースの人なんかじゃなかったよ。高橋くんに顔がそっくりだったというのも、おかしい」
「うん。だから私が会ったのは高橋くんの実のお母さんの方なんだよ」
「実の……?」
「そう。お母さんと一緒にあの家に住んでいるものだと思っていたのに、夏に行ったとき、冷蔵庫も無かったからビックリした。あんな家じゃ、クッキーなんて作れないじゃない?」
このとき、会話の途中で義也くんが黙ってしまったので、里香さんは不安を覚えたのだという。「どうしたの?」と返事を急かすと、ようやっと彼は口を開いた。
「……その女性は幽霊だ。なぜって、高橋くんの実のお母さんは、彼があそこに引っ越してくる前に首吊り自殺したんだからね!」
絶句した里香さんに、彼は続けて説明した。
「高橋というのは彼のお母さんの苗字だ。お父さんが愛人に走り、ご両親が離婚して、お母さんが彼を引き取ったんだ。そしてお母さんは、彼に農薬入りの菓子を食べさせて殺そうとした。
幸い彼は助かった。この事件の後でお母さんは精神病院に入れられて、仮退院したときに、前に住んでいた家で首を吊って自殺したんだって。
彼は母親が死んでも、すぐにはお父さんの戸籍に戻されなかった。だから僕たちの学校に転校してきたときはまだ高橋だったんだ。佐藤というのは父親の苗字だからね。あの家を借りたのはお父さんだったけど、お父さんは愛人の家に住んでいた。間もなく再婚するつもりで。
これを僕は、高橋くんの家にひとりで届け物をしたときに聞いたんだ。
その日、派手なおばさんと男の子が玄関から出てきて、ちょうど帰るところだと僕に言った。自分はこの家に住んでいる子どもの父親の後添いなんだけど、誰もあの子の世話をする者がいないから、ときどき通ってきて面倒をみてやっていると言って、そして、僕にこの話を聞かせたんだ。
僕にはショッキングすぎたよ。ひとりで抱えきれなくて、家に帰ってすぐに母に話した。そしたら、よその家の事情だから誰にも言うなって言われたよ。
僕は、高橋くんがぬいぐるみを刺していたあのとき、おばさんは嘘ついてたんだなって思って悲しかったんだ。面倒みてるって言ってたけど、あの家には何も無かったじゃないか。……酷いよね。僕たち、まだ10歳だったのに」
インタビューの最後に、里香さんはこんなことを私に言った。
「私は高橋くんに本当によく似たおばさんからクッキーを勧められたし、そのクッキーとお皿が地面に落ちて砕けるのも、たしかにこの目で見たんですよ。
あの女性は、本当に高橋くんのお母さんの幽霊だったんですか?
そして高橋くんがクッキーを叩き落としたのは、農薬入りのお菓子を食べさせられたことがあったからなんでしょうか?」
その女性を幽霊だったと決めつけるのは早計かもしれない。里香さんの話から状景を思い浮かべると、幽霊だったような気がしてしまうが、親戚の女性だった可能性も考えられる。
確かなのは、10歳の子どもがひとりぼっちでカーテンも無い部屋に何ヶ月もほったらかされていたことと、彼の死に方と彼の「遊び」が奇妙に符合することだ。
里香さんたちが見た彼のぬいぐるみや塩ビ製の人形は、どれも古びていたという。幼い頃、両親に買い与えられた玩具だったのではあるまいか。
彼が殺したかったのは、そして彼を早すぎる死にいざなったのは、誰か。
※当記事は2018年の記事を再編集して掲載しています。
※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。
関連記事
人気連載
“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】
現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...
2024.10.02 20:00心霊あの子はひとりぼっちだった……少年の“死に方”を決めた“異常な遊び”と謎の幽霊のページです。怪談、実話怪談、情ノ奇譚などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで