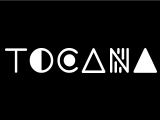セックスを強要する美しすぎる「発光女」の生霊 ― 川奈まり子の実話怪談『いきすだま ~追う女~』
こうして貴司さんはまたしても、精神的に堪えがたい状況に陥ってしまった。
葬儀社ビルのマンションの方も、快適とは言いづらい。
階段や廊下で喪服の集団とすれ違ったり、読経が聞こえてきたり、おまけに、毎日ではないが、かなり頻繁に、壁一枚隔てた向こうに荼毘に付される前の遺体がある次第だ。
線香の匂いの濃さで、使用中か否かがわかるのである。
通夜のときは、真夜中に啜り泣きが聞こえてきた。
また、通夜でもないのに、たまに線香が匂う現象も相変わらずだった。
押し入れは、あれ以降、二度と隙間が開かないように、つっかえ棒で固定していた。
マミが日参するに及んで、上司も事態を次第に真剣に捉えはじめた。
結局、貴司さんは、一時、系列会社に出向させられることになった。
一時と言っても期限が決まっておらず、不本意ではあったが、断れば辞職させられそうな気配で、逆らうことは考えられなかった。
幸い、出向先は実家から近かった。葬儀社のマンションは家賃が激安なこともあり、しばらくの間は戻ってきたときのために借りておくことにして、元のマンションの水道やガスなどの解約手続きを済ませた。
「その後も、上司とは連絡を取り合ってました。マミは、僕がいなくなってからも、ひと月ぐらい、会社の周りに出没しとったそうです。急に来なくなったと報告があり、それと前後して、先輩からも、マミの携帯電話が繋がらなくったと連絡を貰いました。
マンションの退居日が迫ってくると、先輩はわざわざ、その前に掃除する必要があるやろうと考えて、マミの携帯に電話してくれたのだそうです。はい、マンションから出ていったかどうか確かめるために、ですわ。ところが、何度掛けても『お客様がお掛けになった番号は電源が切れているか現在使われていないため……』ちゅうアナウンスが流れるばかりや、と」
そこで、貴司さんは、恐々とマンションに行ってみた。
マミがいた痕跡すら残っておらず、もぬけの殻だったそうだ。ざっと掃除もされていた。
「あの散らかりようからは想像できひんほど、サッパリしたようすになってましてん! 家具や家電も無くなってたんで、ああ、マミは遂に納得して出ていったんだなぁとホッとしたことを憶えとります。せやけど元の会社に戻れたのは、およそ半年後の、お盆の休み明けでした」
葬儀社のビルのマンションは、本当はいけないことだが、春先から先輩の知り合いに又貸ししていた。
何も変わったことは起きなかったと聞いて、安心して部屋を引き渡してもらったその日の夜、異常な寒さで安眠を妨げられた。
真夏ではありえないことだが、震えるほど寒い。
エアコンの温度は27度に設定していた。枕もとに置いておいたリモコンを操作して冷房を切ってみたが、そういう問題ではなさそうだ。まるで冬の戸外のような凍れ方なのだ。
おかしなことはそれだけではなかった。
テレビの画面が砂嵐になっていた。
番組放送終了後の、あの特有の耳障りなノイズ(砂嵐とは、深夜の番組終了後にザーッという雑音と共にテレビ画面に映る白黒のノイズのことで、2012年にアナログ放送が停波するまでは一般的に見られたが、現在の地上デジタル放送には存在しない)に神経を搔き乱される。
音と画面のちらつきがうるさくて寝ていられないのだが……。
点けっぱなしにして寝た覚えがなかった。そもそも、今夜はテレビを見ていなかったのだ。
そのとき、ふいに押し入れの隙間のことが頭をよぎった。
半年以上前、入居したばかりの頃に、夜中に目が覚めると、閉めていたと思った押し入れの戸が細く開いていたことがあった。隙間が開かないようにつっかえ棒をしていたことを忘れていた。ここに帰ってきたときに思い出さなかったのが悔やまれた。
そのとき、ガサッと、砂嵐のノイズとは異なる音が聞こえてきた。
押し入れの方から、だ。
――誰か、いる。
「マミなのか?」
呼びかける声が震えて、か細い。尿道がチクチクして、漏らしそうだ。線香が匂ってきた。
――お通夜をやっとるんや! 隣の安置室で死んだ人の遺族が物音を立てたんや。テレビは寝ぼけて点けたんやし、寒いのはエアコンの故障のせいや! そう思いたい。
視界の隅に、押し入れの戸が入っている。
今度の隙間は大きいぞ!
「タカシくぅん」
何か、青い。
青い塊が、押し入れの隙間から突き出してきた……?
目の端に映っとるだけで充分や! 振り向いてはいけへん。声も、聞こえへん、聞こえへん!
「タぁカぁシくぅん」
マミの声だ。何も知らない者ならば、可愛いらしいとを思うかもしれない、だからこそ一層おぞましい声が。
……さっきよりも近い。
ついに我慢できなくなって、見てしまった。
押し入れの戸を50センチほど開けて、マミの形をした真っ青に光るものがズルズルと這い出してこようとしている。一糸も纏わず、しなやかな裸体を晒している。しかし髪までもが青く、ほのかに発光しているのは、どうしたわけか。
ある種の虫や海洋生物のようだ。しかし、その形はマミそのものだ。
畳に這いつくばったまま、緩慢な仕草で、こちらに手を伸ばして、
「タぁ~カぁ~シぃ~」
と、呼ぶ。微笑む。間違いなくマミの声、マミの笑顔だ。だが青い。
喉から悲鳴を溢れさせて、飛び起きた。
部屋から駆けだす。玄関でサンダルをつっかけ、下駄箱に置いた鍵束を引っ掴む。
その間も、青いマミは後ろで叫びつづけた。
「タカシ・タカシ・タカシ・タカシ・タぁ~カぁ~シぃ~くぅ~ん!」
振り向かずともわかる。這い寄ってきているに違いなかった。転げるように階段を下りて、マンションの駐輪場で自分の自転車に乗った。
玄関の鍵を掛けるのを忘れてしまったことに気づいたが、戻る気にはなれなかった。上は下着メーカーのTシャツ1枚、下はパンツを穿かずに薄っぺらい短パンだけという格好で、財布も持っていない。
こういうとき、頼りに出来そうなのは先輩だけだ。
全速力で自転車を漕いで、10分ほどで先輩のバーに着いた。
「おや、急にどうしたん? あっ! 入るな! とんでもないもんをくっつけてきよった! ちょっと待て!」
ドアを開けた直後、先輩に怖い顔で止められた。カウンターの中から、壺ごと食塩を持ってくると、土俵入りする力士のようにバッサーッと振りかけてきた。
「よし。これでいいやろ。入ってええで。浄めの酒も、はよ一杯いっとけ」
「浄めって……」
先輩は頭を掻いて、「白状するよ」と言った。
「内緒にしててんけど、実は霊感があるんや」
先輩は、幽霊の存在を感じ取れる体質の持ち主で、「葬儀社のマンションはかえって安全だから油断した」とのこと。
「え? 逆やない? 隣がご遺体の安置室なんですよ?」
と、貴司さんが意外に思って訊ねると、「そう思われがちやけど、それが正反対なんや」と先輩は首を振った。
「あっこに連れてこられた亡者は、お坊さんがお経あげたり線香焚いたり、遺族は悼んでくれるし、いたれりつくせりで、みんな成仏してまうからな。しかし、おまえが連れてきたのは生霊やから……」
先輩の見立てでは、その夜、貴司さんに憑いてきたのは、マミの生霊だった。
貴司さんがマンションで青いマミを見たこと、押し入れの戸がひとりでに隙間を開けていたことを話すと、それもマミの仕業だと述べた。
「じゃあ、隣でお通夜をしていないときにも、線香の匂いがときどきしてきたんやけど、それもマミが……?」
「それは違うかもしれないな。でも、さっきも言うたように、あのマンションには逆に幽霊が出づらい。変なことは大方、生霊のせいや」
「なら、今後も現れますか?」
先輩は気の毒そうに貴司さんの顔を見つめた。
「うん。たぶん。彼女があきらめるまでは……」
夜道を独りで帰る勇気はなく、その晩は店に泊まらせてもらった。
関連記事
人気連載
“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】
現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...
2024.10.02 20:00心霊セックスを強要する美しすぎる「発光女」の生霊 ― 川奈まり子の実話怪談『いきすだま ~追う女~』のページです。心霊、怪談、実話、生霊、川奈まり子、情ノ奇譚などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで