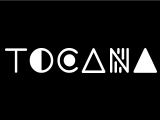セックスを強要する美しすぎる「発光女」の生霊 ― 川奈まり子の実話怪談『いきすだま ~追う女~』
先輩のバーから帰途についたのは翌朝の7時頃だった。平日だったので出社しなければならず、家に帰って着替える必要があったのだ。
葬儀社のマンションから会社までは、バーまでとほぼ等距離の自転車で10分の距離で、10時までに会社に着けばいいから、慌てることはない。
空は明るく晴れ渡り、すでに陽射しが暑い。何の変哲もない真夏の朝だ。国道沿いの歩道の脇をスイスイと走る。歩道にはまだ人影が少なく、プールバッグを提げた小学生たちとすれ違ったぐらい、あとは犬の散歩をしている人を見かけた程度だった。
やがて、工事現場の近くに差し掛かった。路肩に大型トラックが停められていたので、歩道に乗り入れた。自転車で歩道を走ってはいけないが、前にも後ろにも歩行者はおらず、少しだけなら見とがめられることもなかろう。
顔を風が洗う。実に気持ちいい。
――憶えているのは、そこまでだった。
気がつくと地面に横たわっていた。アスファルトの臭いが鼻を衝く。帽子を被った頭が黒いシルエットになって、顔の真上にあった。
若い男だ。警察官のようだ。
「あっ、目が覚めましたね! 大丈夫ですか?」
起きようとすると、体のあちこちが悲鳴をあげた。とくに額がズキズキと痛み、思わず手で押さえると、瘤が出来ていた。微かに湿った感触もある。
「少し血が滲んでますね。そこの電柱にぶつかったんですよ」
男はやはり、すぐ近くの交番に詰めていた巡査だった。
貴司さんは、自分から電信柱にまっしぐらに突っ込んで激突、倒れたのだそうだ。一部始終を目撃した通行人が交番に駆け込んで、知らせてくれたのだ――と、巡査は説明した。
「なんで、そないなことをしたんですか?」
「そう言われても、全然覚えがあらへん。友人のところからチャリで家に帰る途中で、普通に漕いどったんですが、急に意識が飛んで……。 自分から電柱にぶつかっていったって、本当ですか? 直接、その人から話を聞いてみたいなぁ!」
「それが、すぐに立ち去ってしまわれたんですよ。若い女性やったけど」
「若い女性?」
――まさか。
「どんな人でした?」
「まあ、別嬪やった! タレントみたいな……。そんなんより、立てますか? 頭を打っとるから、病院で診てもうた方がいいです。救急車を呼びますか? それともご家族に迎えに来てもらいましょうか? ……どうしました? そないに周りが気になりますか? 誰ぞお連れがいらしたんですか?」
マミがどこかで見ているのではないか、と、思わず辺りを見回して、巡査に不審がられてしまった。
「いいえ、誰も……。独りでした! 大丈夫ですよ! 家はすぐ近くですし、歩いていけます! 会社があるので、帰らないと!」
葬儀社のマンションまでは、実際、そこから100メートル足らずだった。しかし巡査は玄関までついてきた。住所氏名をしっかりと控えていったから、不審者だと思われたのかもしれなかった。本当に大丈夫かと念押しされ、何かあれば連絡するように、と、下駄箱の上に名刺を置いて、ようやく立ち去った。
怪我は恥ずかしいし、不審者扱いは気に障った。が、独りになると、しまったと思った。奥の部屋に入るまで、巡査にいてもらえばよかったのだ。
昨夜逃げ出した部屋に入るのは、勇気が要ることだった。
まずは顔だけ入れて、室内をひとわたり見渡す。
丸めたチリ紙のようになった蒲団。点けっぱなしのテレビに、ニュース番組が映っている。エアコンのスイッチは切れていて、室内は蒸し暑かった。
そして、押し入れの戸は、閉まっていた。
襖紙がしらじらと陽の光を照り返している。
思い切って開けてみたが、不思議な青いマミも、何も潜んでいなかった。
それからは、さほど恐ろしい目にはあっていないと貴司さんは言っていたが、私には賛同できない
確かに彼は、青く発光するマミを二度と見ていないし、彼女のつきまといも止んだ。
あまりにも突然、何も仕掛けられなくなったので、もしかしてマミは死んでいて、青いマミは生霊ではなくて幽霊だったのでは、と思うようになったという。
彼女の勤め先に確認してみたら、ひと月以上前に派遣会社を辞めていた。どこに行ったかはわからずじまいだったから、本当に死んでいる可能性も考えられた。
しかし、とにかく何も起こらないので、次第に彼は穏やかな日常を取り戻していったのである。
ただ、その翌年の1月末か2月頭の頃――マミと別れた季節だ――になって、こんなことがあった。
夜の8時頃、残業していたら携帯電話に非通知の番号から着信があった。出てみたところ、知らない男がいきなり、「マミに酷いことをしたそうだな」と脅しつけてきたのだった。
「なんや、どこの誰ですか?」
「彼の世でマミを預かっとる者だ」
そう男が真面目くさって答えると、その声に後ろから、クスクスという女の笑い声が被さった。
マミだ。マミは生きていた。そして、新手の嫌がらせを考えついたのか。男を使うとはなんと卑怯な。
「彼女、そこにいるんですね?」
遠くからマミが答えた。
「いるわよぉ」
その直後、一方的に電話が切られた
ふざけた電話は、それきり掛かってくることはなかったということだ。
しかし、さらに数年後、貴司さんは、たまたま手に取った男性週刊誌のページの上にマミを見つけた。そこではマミは性風俗店のキャストとして、顔写真付きで雑誌記者のインタビューに答えていた。
「私が風俗嬢になった理由ですか? それはTクンのせいです♡ Tクンが私をセックス大好き人間にしちゃったから、こういうことになったんです♡」
名前が違ったが、顔については見間違えようがなかった。
平成時代の一時、アイドル的な風俗嬢たちが「フードル」と呼ばれて、成人誌などを賑わせていたことがあった。マミは、そのフードルになっていたのだ。
――常識的に考えれば、何も矛盾しない話だ。
行き場も金も無い彼女は、性風俗嬢になり、身近な男に頼んで、貴司さんにイタズラ電話を掛けさせた。ちょっと脅かしてやろうと思い、「彼の世で……」などと不気味なセリフを言わせたのだ。それでもやっぱり彼のことが忘れがたく、雑誌でああいう話をした。おそらく方々で、貴司さんのせいで風俗嬢になったのだと喋っていたのだろう。
私が怖いと思うのは、彼女が彼を忘れていなかった点である。
引き寄せられるように雑誌の彼女を見つけてしまった貴司さんだ。また、いつかどこかで、彼はマミの想いの水脈に触れることになるのではないか。
清姫のように、意中の男を求めて追いすがる執念。それこそが生霊の正体だとしたら、想われているうちは終わっていない。
マミの生霊は、貴司さんの目に映らなくなっただけで、未だに彼に憑いているということになる。
むしろ、彼女が冗談ではなく本当に「彼の世」に旅立っていて、雑誌の風俗嬢が他人の空似なら、その方が怖くないような気がする。
※ 本記事の内容を無断で転載・動画化し、YouTubeやブログなどにアップロードすることを固く禁じます。
関連記事
人気連載
“包帯だらけで笑いながら走り回るピエロ”を目撃した結果…【うえまつそうの連載:島流し奇譚】
現役の体育教師にしてありがながら、ベーシスト、そして怪談師の一面もあわせもつ、う...
2024.10.02 20:00心霊セックスを強要する美しすぎる「発光女」の生霊 ― 川奈まり子の実話怪談『いきすだま ~追う女~』のページです。心霊、怪談、実話、生霊、川奈まり子、情ノ奇譚などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで